最新記事
(05/23)
(05/08)
(12/28)
(12/17)
(12/16)
リンク
プロフィール
HN:
ひか
性別:
女性
自己紹介:
2009年5月第一子出産。主婦のような感じで生活中。
最近またちょっと真面目にイラストとか描いてます。
ブログはほとんど放置ですが、最近ツイッターはそれなりに活用しておるので、こちら↓で生存の確認をして下さい。
最近またちょっと真面目にイラストとか描いてます。
ブログはほとんど放置ですが、最近ツイッターはそれなりに活用しておるので、こちら↓で生存の確認をして下さい。
ついったー。
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター
「私はクリエイターなのよ」って顔して暮らしてたい、そんなこのごろ。

2025/02/02 (Sun)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2008/03/22 (Sat)
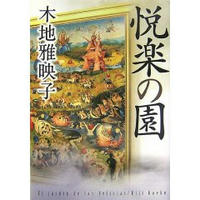
「悦楽の園」木地雅映子(JIVE)
まず、最初に。
私は、どうしてもこの物語を、木地雅映子さんのこれまでの作品、「氷の海のガレオン」「オルタ」ありき・・・で読んでしまう。
だから、読み始めた時には、もうこの物語が何処へ向かおうとするのか・・・何に対して闘いを挑んで行くのかを知っている。
というか、それを期待してページを繰ってしまう。
そうして昨夜読了後、あれ?と思う。
「ガレオン」「オルタ」を知らずに、まったく無防備にこの本を読み始める人は、一体どんな感想を持つんだろう?
それを考えると、ちょっとスリリングですらある。
それくらいに、この物語は“もの凄いところまで”展開する。
ちょっとした刺激を欲している人には、いっそ、この先の私の文章なんか読まずに、この本を手にとってみる事をおすすめしたい。
敷居の高そうなタイトル、装丁と、読み始めてすぐにそのギャップに驚くであろう、軽快な(むしろ軽快すぎる)台詞や語り口。
人によっては、この辺りの入り口に苦手要素があるかも知れないけど。
そこは、是非乗り越えてもらいたい。
誰もが感銘する話ではない、とは思うけど。
無責任でも、私はこの本を、いろんな人に薦めたいと思う。
本を選ぶのに、もう少し慎重であろうと思う人は、続きをどうぞ・・・。
「普通」って何だろうか?
・・・と、いうような事を、誰しも一度くらいは考えると思う。
「普通」が何なのか、きっと、ほとんどの人は明確な答えにたどり着かない。
でも、実体のないそれが、社会の「多数派」だというのはおおむねわかっている。
「普通でいいんだ」と思ってバランス良く生きる人もいると思うし、
「普通なんてまっぴらだ!」と、あえて何か、人と違う事をやろうとする人もいると思う。
無自覚に、或いは自覚していても、どうも普通でいられない、
どうしたってはみ出して行ってしまう人・・・というのもいると思う。
この物語に出てくる中一の少年、南一は、この3つ目に該当する。それも、突出して。
「普通」でない人にとって、この社会は生きにくい。
「学校」へ行かなければならない子供のうちは、ことさら。
子供同士は容赦ないし、理解のない大人は落ちこぼれと看做して尻を叩く。
そんな南に惹かれた主人公の真琴が、南が潰されないよう、奮闘を始める。
南は「発達障害」と診断される一方、特異な絵の才能を持ち合わせる。
そんな明らかに「特別」な南を中核に描かれるけど、
世の中には「そこまでではないけど、あんまり真ん中に寄れない」人たちもたくさんいる。
南ほどの免罪符は与えられないけれども、それぞれに、きっと自然な立ち位置がある。
真琴の実家に集まる不登校の子供達、
隣のクラスの不良少年染谷君、
真琴の画策により、個性を発揮しだす同級生。
そして、真琴自身も決して「真ん中」にいる人間ではない。
「普通」って何だろうか?
そこに入れない人間は、どうやって生きて行けばいいんだろうか?
というテーマを孕みながら、それでいて物語は軽快な学園ドラマのように進み、
でも実は「早婚の女系家族に生まれた13歳の少女の、妥協のない激甘恋愛ストーリー」です。
すごいな、すごいだろう。
何故この物語を、重苦しい純文学のような装丁で出版してしまったんだろう?
いっそ、ピンクの爽やかな表紙で、携帯小説が並ぶエンドの平台にでも混ぜておけば
真琴と同じ年回りの少女たちが手にとって、まんまと木地ワールドに引き込まれたに違いないのに!・・・とか思います。
登場人物の設定、展開、非現実に過ぎるところ、都合が良すぎるところ、
つっこまずにいられないところはいくつもあるんですが。
そんなものはいいんだ、つっこみながら読め!
・・・と、大絶賛するのは、きっと自分が「真ん中」と自分とのちょうどいい距離の取り方がヘタクソなまま歳をとってきているから。
基本的には、中学生とか、高校生とかに読んで欲しい本。
でも、自分みたいなヘタクソな大人も絶対大勢いるので、手当り次第に薦めたいのです。
「悦楽の園」木地雅映子(JIVE)
まず、最初に。
私は、どうしてもこの物語を、木地雅映子さんのこれまでの作品、「氷の海のガレオン」「オルタ」ありき・・・で読んでしまう。
だから、読み始めた時には、もうこの物語が何処へ向かおうとするのか・・・何に対して闘いを挑んで行くのかを知っている。
というか、それを期待してページを繰ってしまう。
そうして昨夜読了後、あれ?と思う。
「ガレオン」「オルタ」を知らずに、まったく無防備にこの本を読み始める人は、一体どんな感想を持つんだろう?
それを考えると、ちょっとスリリングですらある。
それくらいに、この物語は“もの凄いところまで”展開する。
ちょっとした刺激を欲している人には、いっそ、この先の私の文章なんか読まずに、この本を手にとってみる事をおすすめしたい。
敷居の高そうなタイトル、装丁と、読み始めてすぐにそのギャップに驚くであろう、軽快な(むしろ軽快すぎる)台詞や語り口。
人によっては、この辺りの入り口に苦手要素があるかも知れないけど。
そこは、是非乗り越えてもらいたい。
誰もが感銘する話ではない、とは思うけど。
無責任でも、私はこの本を、いろんな人に薦めたいと思う。
本を選ぶのに、もう少し慎重であろうと思う人は、続きをどうぞ・・・。
「普通」って何だろうか?
・・・と、いうような事を、誰しも一度くらいは考えると思う。
「普通」が何なのか、きっと、ほとんどの人は明確な答えにたどり着かない。
でも、実体のないそれが、社会の「多数派」だというのはおおむねわかっている。
「普通でいいんだ」と思ってバランス良く生きる人もいると思うし、
「普通なんてまっぴらだ!」と、あえて何か、人と違う事をやろうとする人もいると思う。
無自覚に、或いは自覚していても、どうも普通でいられない、
どうしたってはみ出して行ってしまう人・・・というのもいると思う。
この物語に出てくる中一の少年、南一は、この3つ目に該当する。それも、突出して。
「普通」でない人にとって、この社会は生きにくい。
「学校」へ行かなければならない子供のうちは、ことさら。
子供同士は容赦ないし、理解のない大人は落ちこぼれと看做して尻を叩く。
そんな南に惹かれた主人公の真琴が、南が潰されないよう、奮闘を始める。
南は「発達障害」と診断される一方、特異な絵の才能を持ち合わせる。
そんな明らかに「特別」な南を中核に描かれるけど、
世の中には「そこまでではないけど、あんまり真ん中に寄れない」人たちもたくさんいる。
南ほどの免罪符は与えられないけれども、それぞれに、きっと自然な立ち位置がある。
真琴の実家に集まる不登校の子供達、
隣のクラスの不良少年染谷君、
真琴の画策により、個性を発揮しだす同級生。
そして、真琴自身も決して「真ん中」にいる人間ではない。
「普通」って何だろうか?
そこに入れない人間は、どうやって生きて行けばいいんだろうか?
というテーマを孕みながら、それでいて物語は軽快な学園ドラマのように進み、
でも実は「早婚の女系家族に生まれた13歳の少女の、妥協のない激甘恋愛ストーリー」です。
すごいな、すごいだろう。
何故この物語を、重苦しい純文学のような装丁で出版してしまったんだろう?
いっそ、ピンクの爽やかな表紙で、携帯小説が並ぶエンドの平台にでも混ぜておけば
真琴と同じ年回りの少女たちが手にとって、まんまと木地ワールドに引き込まれたに違いないのに!・・・とか思います。
登場人物の設定、展開、非現実に過ぎるところ、都合が良すぎるところ、
つっこまずにいられないところはいくつもあるんですが。
そんなものはいいんだ、つっこみながら読め!
・・・と、大絶賛するのは、きっと自分が「真ん中」と自分とのちょうどいい距離の取り方がヘタクソなまま歳をとってきているから。
基本的には、中学生とか、高校生とかに読んで欲しい本。
でも、自分みたいなヘタクソな大人も絶対大勢いるので、手当り次第に薦めたいのです。
PR
この記事にコメントする

