最新記事
(05/23)
(05/08)
(12/28)
(12/17)
(12/16)
リンク
プロフィール
HN:
ひか
性別:
女性
自己紹介:
2009年5月第一子出産。主婦のような感じで生活中。
最近またちょっと真面目にイラストとか描いてます。
ブログはほとんど放置ですが、最近ツイッターはそれなりに活用しておるので、こちら↓で生存の確認をして下さい。
最近またちょっと真面目にイラストとか描いてます。
ブログはほとんど放置ですが、最近ツイッターはそれなりに活用しておるので、こちら↓で生存の確認をして下さい。
ついったー。
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター
「私はクリエイターなのよ」って顔して暮らしてたい、そんなこのごろ。

2025/02/09 (Sun)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2008/03/29 (Sat)
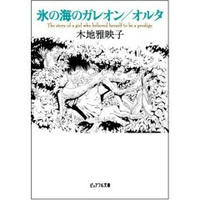
「氷の海のガレオン/オルタ」木地雅映子(ピュアフル文庫)
もしも、「今まで読んだ本で好きな本は?」と聞かれたら、私はベスト5の中に、確実にこの本を入れる。
でも、これが「今まで読んだ本で面白かった本は?」とか、或いは「お薦めの本を教えて」というような質問だとちょっと話が違ってくる。
“おもしろい”という言い回しはちょっと相応しくないし、お薦めかどうかについては、その会話の相手によって180度変わってしまう。
この本が好きだ、という人は、きっとそれは猛烈に好きであるに違いなく、そして私がそうであったように、何か強烈で重大な何かをこの本から受け取るはずだ。
そうでない人には、特に面白くもなく、なんだか良くわからず、もしかしたら主人公の性格が気に障る人もいるかもしれない。
多分、中間はない。
「氷の海のガレオン/オルタ」木地雅映子(ピュアフル文庫)
もしも、「今まで読んだ本で好きな本は?」と聞かれたら、私はベスト5の中に、確実にこの本を入れる。
でも、これが「今まで読んだ本で面白かった本は?」とか、或いは「お薦めの本を教えて」というような質問だとちょっと話が違ってくる。
“おもしろい”という言い回しはちょっと相応しくないし、お薦めかどうかについては、その会話の相手によって180度変わってしまう。
この本が好きだ、という人は、きっとそれは猛烈に好きであるに違いなく、そして私がそうであったように、何か強烈で重大な何かをこの本から受け取るはずだ。
そうでない人には、特に面白くもなく、なんだか良くわからず、もしかしたら主人公の性格が気に障る人もいるかもしれない。
多分、中間はない。
主人公の杉子の事は、よく使われる言葉で言うと「クラスで浮いている子」という事になるんだろうか。
別に、ひどくいじめられているという訳ではない。ただ、クラスの多数派の子供たちとは違う価値観を持っている。そのために、「異物」という扱いを受けている。
変わり者の両親の影響(或いは、血)で、十一歳としては少々発達しすぎた自我を持ち、“みんながこれがいいって言うもの、あたしはちっともそう思わない”。文学と、パパとママの言葉によって培われた“自分の言葉”は、同じ日本語なのに学校では通用しない。
みんなと同じでないというだけで、それをバッシングの対象としようとする「集団」の中で、杉子は、自分は天才であると信じ、「体だけ同い年のばかどもには、高尚すぎて足下にも寄れないような本」を携え、孤立して生活している。
庭のナツメの大木、ハロウに語りかけ、一人そこに身を委ねる。
杉子の本心は、具体的な言葉では語られない。
ただ、会話の中や語りの断片に、杉子自身にもはっきりと認識しない感情を覗かせる。
もしかしたら、わかっているのかもしれない。認めたくないだけなのかもしれない。
いや、でもやっぱりはっきりとはわからない・・・。
それが、またリアリティがある。
“クラスの中で孤立する一人”というシチュエーションで物語が始まった場合、それが若年向けに書かれたものであればほぼ間違いなく、「みんな仲良くなってハッピーエンド」という結末に向かいたがる。
でも、「ガレオン」はそっちへは行かない。
だから、結論として、その断面からはこの物語は解決しない。
でも、そこがありがたい。
そんなものは、望まない。と思う。
杉子が、理解者となる音楽教師の多恵子さんと出会い、その事をママが「あの子にとって、あなたは大きなよろこび」と語ったように。
この本に出会うべくして出会った人には、きっとこの本を「大きなよろこび」と感じる。
自分が今立っている場所が、恥ずべき場所ではないと、きっと思える。
別に、面白くはない。
為になるわけでもない。
ただ、とにかく楽になる。許される。
だから、私は本当にこの物語が好きだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
他に、文庫化にあたって書き下ろされた「オルタ」が収録されている。
はっきりと明記されているわけではないのだけど、おそらく木地雅映子さんと、その娘さんの実話(或いはそれをモデルにした物語)。
「氷の海のガレオン」と同じく、「学校(=集団)」と、そこに馴染まない(向いていない)「個人」の物語が、母親の視点から語られる。
漠然と「孤独」であった杉子から一歩踏み込んで、自閉症児や、その疑いのある子供、グレーゾーンにいる子供という具体的な存在をとりあげて、警鐘を鳴らす。或いは、問いかける。
きっと本当に、木地雅映子さん自身が悩んだり、知りたかったり、それから子供たちやその親である大人たちに知って欲しいと思った事をガンガン書いてやったんだろうな、というような文章です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最初に書いたように、面白いかどうかとか、物語として良く出来ているかとか、そういった観点で言えば、まったく「お薦めの本」ではないんですが。
でもとにかく、これを書く人がいるという事が、それが印刷されて書店に置いてあるという事が、私にはとてつもなく嬉しい。
そういう本です。
余談ですが、表紙イラストはあの松本大洋さん。
文庫版ではモノクロの線画になってしまったのですが、絶版になった単行本では強烈な色彩で彩色されていて、味わい深いタイトル文字のインパクトもすばらしく、ぱっと見た瞬間に手にとらずにいられないような、そんなデザインでした。
別に、ひどくいじめられているという訳ではない。ただ、クラスの多数派の子供たちとは違う価値観を持っている。そのために、「異物」という扱いを受けている。
変わり者の両親の影響(或いは、血)で、十一歳としては少々発達しすぎた自我を持ち、“みんながこれがいいって言うもの、あたしはちっともそう思わない”。文学と、パパとママの言葉によって培われた“自分の言葉”は、同じ日本語なのに学校では通用しない。
みんなと同じでないというだけで、それをバッシングの対象としようとする「集団」の中で、杉子は、自分は天才であると信じ、「体だけ同い年のばかどもには、高尚すぎて足下にも寄れないような本」を携え、孤立して生活している。
庭のナツメの大木、ハロウに語りかけ、一人そこに身を委ねる。
杉子の本心は、具体的な言葉では語られない。
ただ、会話の中や語りの断片に、杉子自身にもはっきりと認識しない感情を覗かせる。
もしかしたら、わかっているのかもしれない。認めたくないだけなのかもしれない。
いや、でもやっぱりはっきりとはわからない・・・。
それが、またリアリティがある。
“クラスの中で孤立する一人”というシチュエーションで物語が始まった場合、それが若年向けに書かれたものであればほぼ間違いなく、「みんな仲良くなってハッピーエンド」という結末に向かいたがる。
でも、「ガレオン」はそっちへは行かない。
だから、結論として、その断面からはこの物語は解決しない。
でも、そこがありがたい。
そんなものは、望まない。と思う。
杉子が、理解者となる音楽教師の多恵子さんと出会い、その事をママが「あの子にとって、あなたは大きなよろこび」と語ったように。
この本に出会うべくして出会った人には、きっとこの本を「大きなよろこび」と感じる。
自分が今立っている場所が、恥ずべき場所ではないと、きっと思える。
別に、面白くはない。
為になるわけでもない。
ただ、とにかく楽になる。許される。
だから、私は本当にこの物語が好きだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
他に、文庫化にあたって書き下ろされた「オルタ」が収録されている。
はっきりと明記されているわけではないのだけど、おそらく木地雅映子さんと、その娘さんの実話(或いはそれをモデルにした物語)。
「氷の海のガレオン」と同じく、「学校(=集団)」と、そこに馴染まない(向いていない)「個人」の物語が、母親の視点から語られる。
漠然と「孤独」であった杉子から一歩踏み込んで、自閉症児や、その疑いのある子供、グレーゾーンにいる子供という具体的な存在をとりあげて、警鐘を鳴らす。或いは、問いかける。
きっと本当に、木地雅映子さん自身が悩んだり、知りたかったり、それから子供たちやその親である大人たちに知って欲しいと思った事をガンガン書いてやったんだろうな、というような文章です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最初に書いたように、面白いかどうかとか、物語として良く出来ているかとか、そういった観点で言えば、まったく「お薦めの本」ではないんですが。
でもとにかく、これを書く人がいるという事が、それが印刷されて書店に置いてあるという事が、私にはとてつもなく嬉しい。
そういう本です。
余談ですが、表紙イラストはあの松本大洋さん。
文庫版ではモノクロの線画になってしまったのですが、絶版になった単行本では強烈な色彩で彩色されていて、味わい深いタイトル文字のインパクトもすばらしく、ぱっと見た瞬間に手にとらずにいられないような、そんなデザインでした。
PR
この記事にコメントする

